青森県に『数字』と『戸(のへ)』がつく地名が多い理由【四戸はない】
 青森県と岩手県には、1~9といった数字と戸(のへ)のつく地名が多くあります。
青森県と岩手県には、1~9といった数字と戸(のへ)のつく地名が多くあります。
三戸町・五戸町・六戸町・七戸町・八戸市
岩手県
一戸町・二戸市・九戸村
読み方は、『~のへ』。

UOTO
なんとなく不思議だと思いませんか?
しかもよく見ると『四戸』だけがありません。
青森や岩手になぜこのような数字+戸(のへ)がつく地名が多いのか、なぜ四戸がないのかを書いていきたいと思います。
数字と戸(のへ)がつく地名が多い理由
なぜ青森県南部と岩手県北部には1~9の数字に戸(へ)が付く地名が多いのか?
可能性の一つとして考えられているのが、
です。
1070年頃の【延久蝦夷合戦】で蝦夷から手に入れた土地を分けた際に、現在の青森県東部~岩手県北部にかけて広大な『糠部郡』が設置されました。
その後、軍功をあげた甲斐国南部氏が糠部郡を授かり、馬の生産が盛んだった広い糠部郡をさらに9つに分けて誕生したのが、この~のへになります。
「戸(のへ)」というのは牧場や集落・行政区画という意味があり、当時は町名とかではなく地区名くらいの考え方だったと思います。
しかし蝦夷征伐の際に設置された柵戸(きへ)説など諸説あり、未だに結論が出ていないのが現状です。

UOTO
なぜ四戸だけがない!?
1~9という数字が付く街があるといっても、実は「4」、四戸だけがありません。
実は最初から無かったわけではなく、江戸時代くらいまでは『四戸』という地名はあったそうです。
その四戸があったの場所としては有力なのは、
・五戸浅水説

八戸市八幡地区には『櫛引八幡宮』という重要文化財がありますが、当時は『四戸八幡宮』と呼ばれていました。
なのでその辺りの地域一帯が『四戸』だったのでは?と言われています。
実際に1366年の日付がある『四戸八幡宮神役帳』には、四戸という地名も記載されているそうです。
もう一つの五戸浅水説に関しては、『浅水』という地名が元々『朝見ず』という意味からきているそうで、
と変わっていったそうな。
地理的にも五戸と三戸の間ということもあり、浅水地区が四戸だった可能性は確かに無きにしも非ずですね。
ちなみに、なぜ四戸だけがなくなったのかについては不明だそうです。
単純に「4は縁起が悪いから」と思ってしまいがちですが、当時の人がそこまで考えていないような気がします。

UOTO
無くなりかけた、戸(のへ)がつく地名
そんな歴史のある「戸(のへ)」がつく地名ですが、実は平成の大合併で無くなりかけました。
まず「七戸町」。
2000年代に全国の市町村で実施された平成の大合併で、七戸町も周辺4町村での合併でなくなりかけました。
その後、合併協議が頓挫して2町村合併で七戸という名を残したのです。
次に「六戸町」。
こちらも周辺3町での合併を協議し町名が無くなりかけましたが、色々あって離脱という形をとって町名が残ることに。
最後に「一戸町と九戸村」。
こちらは二戸市を中心とした広域合併の協議を打ち出しましたが、一戸町と九戸村などは賛同せず一部合併にとどまり、町名・村名を残しています。

UOTO
面白い「数字+戸(のへ)」の世界

この記事を作るにあたって色々調べたのですが、低学歴には難しすぎて薄い内容になってしまいました。
簡単に言えば、元々馬の産地だった広い糠部郡を9つの牧場集落(戸)に分けた事が「~のへ」の始まりってことですかね。※諸説あり
そして面白いのが東北新幹線。
3駅連続で「戸(のへ)」のつく駅名になっています。

UOTO
全国的にもナンバリングしてある市町村名はなかなかないかと思います。
ぜひ青森県や岩手県へ観光される際は、この「数字+戸(のへ)」のつく地名をコンプリートしてみてはいかがでしょうか?
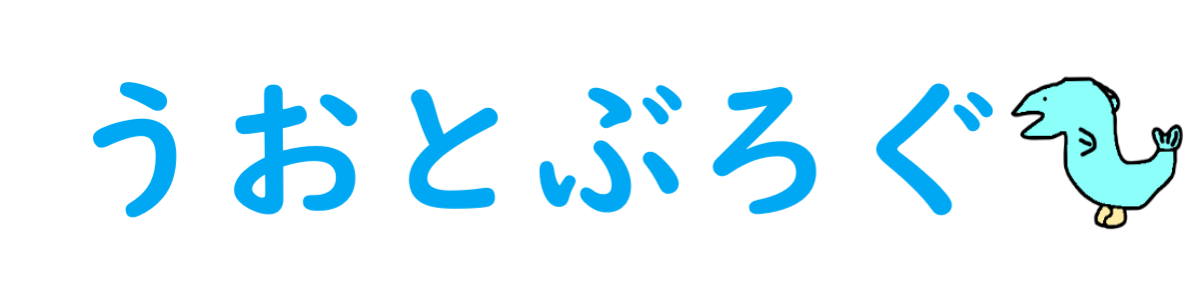
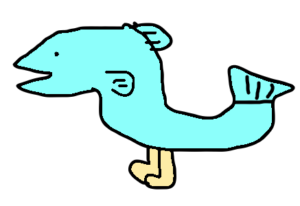



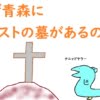

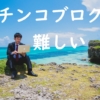












ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません