 いきなりですが、みなさんは長生きしたいですか?
いきなりですが、みなさんは長生きしたいですか?
自分がどのくらい長生きするのかは未来のことなので分からないものですが、都道府県の平均寿命を見ると目標的なのが見えてきます。

※2015年データ
こちらは2015年の都道府県の平均寿命上位3県と下位3県を表した表です。
ぱっと見でお気づきの方もいらっしゃるでしょうけど、実は青森県の平均寿命は男女ともに全国最下位なんです。
男性に関しては、1位滋賀県との差がなんと約3年。

UOTO
そのせいか健康番組でも悪い例として取り上げられ、青森県は『短命県』というレッテルを貼られてしまっています。
青森県が生産量1位のりんごは「1日1個のりんごは医者を遠ざける」と言われるほどの健康フルーツだし、同じく生産量1位のにんにくだって言わずと知れた健康食材。
そういった健康的な食材豊富の青森県がなぜ“短命県”なのか?
その理由を考えてみます。

UOTO
青森県が短命県の理由

青森県の短命県が注目されたのは健康志向が高まった近年と記憶していますが、実はかなり前から日本一の短命県でした。
上位との差は縮んできているものの、男性は【70年代】から女性は【90年代】からずっと全国最下位なのです。
その死因は、病気がほとんど。
・悪性新生物(各種がん):34.4%
全国順位(男1位:女1位)
・心疾患(心筋梗塞など):13.1%
全国順位(男6位:女16位)
・脳血管疾患(脳梗塞など):9.0%
全国順位(男1位:女3位)
・肺炎:8.4%
全国順位(男1位:女4位)
・自殺:4.5%
全国順位(男11位:女40位)
※順位が高いほど悪いって意味です
となっています。

UOTO
病気で死亡する人が多いということは、生活面に問題があるのでは?と思ってしまいますよね。
青森県が短命県である4つの理由を挙げてみます。
食生活(塩分の摂り過ぎなど)

青森県が短命県である理由は、食生活に問題があるかもしれません。
青森県はラーメン好きの人が多く、特にカップラーメンは気軽に食べられ寒さをしのげる事から、他県よりも購入量が多くなっています。
1位 青森市 8403g
2位 富山市 8243g
3位 山形市 8224g
4位 新潟市 7717g
5位 鳥取市 7575g
参考:総務省統計局家計調査 2014年
そしてスープが大好きな人も多く、飲み干すのがデフォです。
ラーメンのスープまで飲み干すと、1日分の塩分を摂ることになってしまいます。
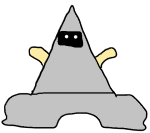
アス・パム男
こういった塩分の摂り過ぎで病気になってしまうのかもしません。
また2018年の統計では、青森県の糖尿病死亡率は全国1位となっていました。
その理由かもしれないランキングがこちら・・・。
1位 青森市 6748円
2位 宇都宮市 5424円
3位 山形市 5385円
参考:総務省家計調査2011~2013平均
コーヒー飲料購入量(1世帯当たり年間)
1位 福井市 6274円
2位 新潟市 4769円
3位 青森市 4743円
参考:総務省家計調査2011~2013平均

UOTO
炭酸飲料や缶コーヒーは糖分が多く含まれているため、糖尿病のリスクが高まります。
庶民で初めてコーヒーを飲んだのが青森県人という歴史もあるとはいえ、ブラックならまだしも甘い缶コーヒーは体に害だと思います。
青森あるある記事にも書きましたが、青森県にはまとめ買い文化というのもあり、箱買いする家庭も多く、そこから食べ過ぎ・飲みすぎにも繋がっているのかもしれないですね。
喫煙率の高さ

青森県は、男女共に喫煙率は高い傾向にあります。
1位 北海道 24.7
2位 青森県 23.8
3位 岩手県 22.6
4位 福島県 22.4
5位 群馬県 22.0
こちらのハッキリとした理由は不明ですが、農家や漁師の喫煙者が多い事を考えると、青森県は第一次産業就業者割合が高いのでそれが影響しているのではないかと考えます。
喫煙率の高い都道府県を見てみると、北海道・東北関東が上位に来ていますので地域柄って言った方がいいのかもしれません。

UOTO
運動不足

ネット上にはこんな声がありました。
これは間違いでもあり、正解でもあります。

UOTO
なぜ間違いかというと、平均寿命の上位に同じ雪国である長野県や新潟県がいることを考えれば、雪が多いから運動不足ということにはなりません。
しかし雪を言い訳にして運動しない青森県民も確かに存在し、新聞の統計でも8割の県民が「運動不足」を自覚しているそうです。
引用:朝日新聞デジタル
車での移動や家で籠ることに慣れてしまい、運動不足になっているのかもしれません。

UOTO
病院に行かない人が多い?

食生活が悪くて、喫煙率も高い、そして運動もしないとなると、そりゃ短命県にもなるって話ですが、実はそれだけではなく、体調が悪くても病院に行かない人が多いという理由もあります。
例えば悪性新生物(がん)に関して、長寿県である長野県と比べても罹患率はさほど変わらないそうです。

UOTO
国立がん研究センターの『2014年のがん罹患者の進展度分布』によると、限局率(最初に発生した臓器意外に広がっていない率)は、
長野県:47.4%
全国平均:44.7%
となっており、青森県でがんが見つかったときには進行している場合が多いそうです。
つまり青森県の悪性新生物による死亡率が高いのは、多少体調が悪くても病院に行かず、その後見つかったときにはもう手遅れってことが多いから。

UOTO
青森県が短命県なのは『健康に対する意識の低さ』

青森県が短命県の理由をまとめます。
・喫煙率の高さ
・運動不足
・病院に行かない人が多い
以上の4つが短命である大きな理由で、極論を言えば『県民の健康に対する意識の低さ』が原因だと思います。
長生きしたいと思えば、自然と食生活も改善するだろうし、タバコも吸わなくなります。
しかし未だにワーストだということを考えれば、やはり意識の問題でしょう。
青森県では【短命県返上キャンペーン】を必死に行っています。
短命県最下位から脱却を目指す取り組みですが、あまり県民には届いていない気もしています。

UOTO
平均寿命というのは、短い期間で解決するものではありません。
日々の積み重ねが、結果的に長寿に結びつきます。
青森県のため・・・というよりも、自分のために今から生活改善していきましょう。

UOTO
・青森県人に肥満が多い理由【全国ワースト】
・持ち歩きできるリンゴ酢を飲んでみた感想【リンゴ酢の効果についても!】
・青森のごぼう茶を飲んでみた感想【ごぼう茶の効果は?まずい?】
ちなみに青森県の『健康寿命』は・・・
追記になりますが、『平均寿命』は全国最下位が続く青森県ですが、『健康寿命』はどうなのか?をみていきます。
青森県の女性は『平均寿命』こそ最下位ですが、『健康寿命』は全国13位。
ただ寿命を延ばすだけでなく、健康に生活できることも考えていきましょう。

UOTO


コメント